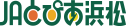
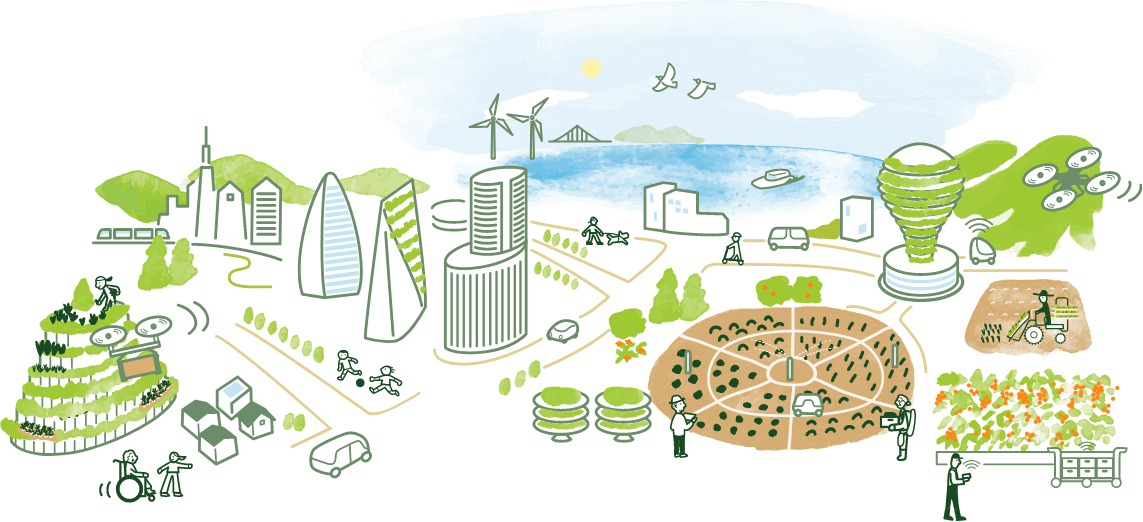
SDGsは、人間、地球および繁栄のための行動計画です。世界中で達成すべきゴールに向かって活動や行動を促進し、
日本でも政府や企業、学校教育、地域社会等で、SDGsのゴールに向けた活動が実践されています。
JAグループもSDGsに賛同し、その達成に向けて事業や活動に取り組むと宣言しています。


複数の施策で新たな担い手を育成支援
農業の生産力強化と持続可能性の向上を実現するため、当組合では複数の施策で新たな担い手の育成に取り組んでいます。農業の基礎知識から幅広い内容を習得する「とぴあ園芸教室」を開講する他、品目特化型の「パセリの楽園プロジェクト」や「エシャレット養成塾」など、部会、協議会ごとに独自の担い手支援策を講じています。

新しい肥料の開発や廃プラスチックの回収で環境負荷を低減
当組合が開発した肥料「ecoみどり配合」は、生産コストの低減を一番に考えて開発した肥料であると同時に、食品残渣を原材料とし、国の「みどり食料システム戦略」に基づいた生産やSDGsに配慮した循環型肥料です。また、定期的にビニールやマルチを回収する「使用済プラスチック回収」を行うなど、環境負荷低減に努めています。
持続可能な農業を目指してみどり食料システム戦略への取り組み
「みどり食料システム戦略」は、国内農林水産業の生産力強化や、持続可能性の向上を目指し、2021年に農林水産省が策定した食料生産の方針です。戦略策定の背景には、地球温暖化や大規模な自然災害などの環境問題があります。そのため、2050年までに化学農薬の使用量を50%低減、化学肥料の使用量を30%低減などの目標を掲げています。当組合も「ecoみどり配合の開発」「スマート農業」「品目ごとの担い手育成」などに取り組んでいます。

スマート農業で生産力強化と持続可能性を両立
農業の生産力向上と持続性の両立をイノベーション(新機軸・技術革新)で実現しようと、さまざまな取り組みが行われています。GPSと連動した自動運転や、人工衛星の情報を使った生育管理システム、ドローンを使った施肥や農薬散布などのスマート農業について、当組合でも試験を始めています。

地産地消で環境への配慮と農家所得向上を
地元農産物を優先的に使えば、輸送時の燃料や梱包資材の使用を減らすことにつながります。ファーマーズマーケットは、魅力的な売り場づくりでフードマイレージの縮小に貢献します。また、環境への配慮と同時に、農家所得の向上にも寄与するため、ビニール袋などの梱包資材の簡素化、レジ袋の有料化や雑がみ回収袋の配布にも取り組んでいます。

子ども食堂への食材提供で地元野菜のおいしさをPR
JAとぴあ浜松のファーマーズマーケットでは、4店舗それぞれの出荷者協議会が、地域の子ども食堂へ食材提供を行っています。この活動は、子ども食堂の支援や食品ロスの軽減だけでなく、子ども食堂の利用者に、地元農産物のおいしさを知ってもらい、地元食材のファンを増やすという意義もあり、多くの出荷者の協力のもとに成り立っています。

規格の簡素化や原料加工で循環型農業を実現
とぴあでは、セルリーの出荷調整時に出るかき葉(外葉)などを、パウダーや圧搾汁に加工する原料として出荷しています。また、パセリや砂糖えんどう、オクラなどで、複数の規格を組み合わせて販売する取り組みも行っています。規格の簡素化により出荷の幅を広げ、食品ロスを軽減すると同時に、農家所得の向上に取り組みます。
地産地消の推進と食料安定供給の両輪でSDGsに取り組みます
とぴあ管内は、全国有数の農業地帯です。ファーマーズマーケットを拠点とした地産地消の推進はもちろん、梱包資材の簡素化を実現する売り場の工夫や、出荷者協議会による子ども食堂への食材提供など、SDGsを意識した取り組みを進めています。一方、都市の人々に、安定して食料を供給するのも、産地としての責任です。出荷規格を簡素化した販売や、加工原料への対応を通して、食品ロスの低減と農家所得の向上に取り組んでいます。

再生可能エネルギーの利用促進による住環境向上への支援
金融推進部では、組合員・利用者の皆さまから選ばれ必要とされ続ける金融機関を目指し、きめ細かな提案を行い、サービスを提供していきます。エコカーの購入や、太陽光発電設備設置などリフォームに必要となる資金をお借り入れの際には、金利軽減をしています(※詳しい内容は各支店へお問い合わせください)。また、特殊詐欺への注意喚起のため、職員によるチラシ配布や日常的な声掛けを行い、安全で暮らしやすい地域の実現に向けて取り組んでいます。

相談機能の充実を図り、部門間連携で地域農業の発展に寄与
金融管理部では、組合員の相談機能の充実を図り、支店や営農部門とも連携し、融資を通じて地域農業の発展に貢献しています。明日の農業を担う農業者を支援するため、農機具、倉庫、ビニールハウスなどの設備資金の他、農産物の生産・加工・流通・販売に必要な運転資金を低金利でサポートします。また、営農アドバイザーと支店融資担当者が同行し、農家宅を訪問して経営意向を伺う「担い手支援訪問活動」を実施しています。

健康で豊かな生活への貢献
共済部では、JA共済の生命共済加入世帯と団体(契約保障額2, 500万以上/年度末)のうち、生命共済被共済者おひとりにJA静岡厚生連遠州病院での人間ドック受診料の一部を助成しています。加入者の皆さまの幸福と安定した豊かな生活づくりを、健康管理や健康増進、生活習慣病予防の観点から、お手伝いしています。

生活を再建し住み続けられるまちづくり
近年、発生した線状降水帯による記録的な大雨で、とぴあ管内でも大規模な浸水や土砂被害が発生しました。突然襲い掛かる自然の脅威に対し、いち早く生活の再建ができるよう、建物更生共済加入者への速やかな共済金支払いに努めています。加入者の経済的不安を払拭して安心を提供します。

JA共済の地域貢献活動でCO2抑制とコスト低減
野菜や水稲の苗を供給する「総合育苗センター」では、施設の加温に重油を使用してきましたが、近年、新たに地下水の熱を利用するシステムを導入し、重油と地下水を併用するハイブリッド式に移行しました。これにより、CO2の排出抑制と燃料コスト低減を目指しています。この事業にはJA共済の地域貢献活動(地域・農業活性化促進助成金制度)が活用されています。
地域に根差したJA共済の役割を果たす
JA共済は「相互扶助」を事業活動の原点として「ひと・いえ・くるまの総合保障」の提供や、地域貢献活動を通じ、組合員・利用者・地域住民の皆さまが豊かで安心して暮らすことのできる地域社会を目指しています。とぴあ管内の60支店は、地域のインフラとして、きめ細やかな相談業務をはじめ、罹災時の迅速な共済金の支払いに努め、皆さまの暮らしを支えます。今後も地域に寄り添い組合員・利用者から信頼され、住み続けられるまちづくりに貢献していきます。

女性部活動そのものがSDGs
JA女性組織は、約70年前に全国各地で設立されました。食と農を基軸に、時代や地域ごとの要望に合わせて活動を展開し、女性の経済的社会的地位の向上、生きがいづくりなどを行ってきました。「エッセンスセミナー」は、子育て世代の女性を対象に「食」や「農」を中心にJAならではのカリキュラムを行う講座。時代のニーズに合わせて進化する女性部活動の一つです。

朝ごはん食べよう料理教室
高校生に、伝統的な朝ごはんのおいしさや重要性を伝えるために毎年行っている活動です。

フードドライブ
各家庭で使いきれない未使用の食材を集めて、フードバンク団体や福祉施設などに寄贈する活動です。集まった食品は食べ物に困っている人や施設に配られます。

元気高齢者のお手伝い
浜松市浜名区新原にある「ふれあいセンター槙の里」では、高齢者の生きがいづくりや、地域住民の居場所づくりのお手伝いをしています。利用者は、ペタボードなどのレクリエーションや保健師による健康講話で仲間と楽しく過ごします。昼食には地元野菜を使った女性部員手作りのお弁当を提供し、地産地消にも貢献しています。
地域の皆さまのためにSDGsに沿った事業を展開
食と農の大切さを知ってもらう食育活動、食品ロスの削減を目的としたフードドライブ活動、高齢者を支える助けあい活動など、女性部の活動は、まさにSDGsそのものです。さらに、生活事業には、皆さまが将来にわたって住み続けられる地域を目指す資産管理事業や、管内で生産される花の一部を使用し、利用者に寄り添った葬儀を行う葬祭事業もあります。これからも、SDGsに沿った事業を展開して地域活性化や農業振興に貢献していきます。